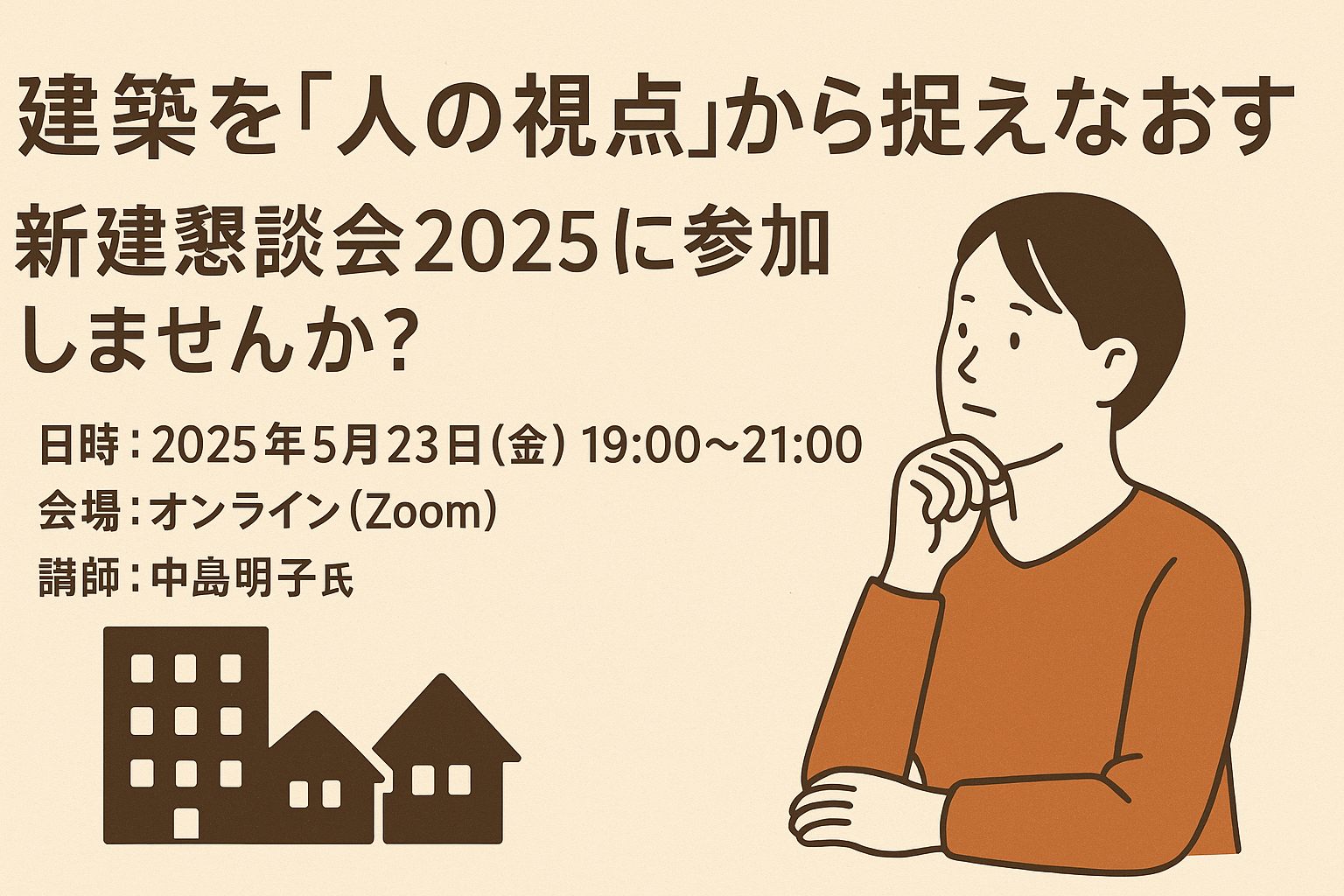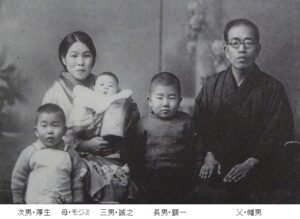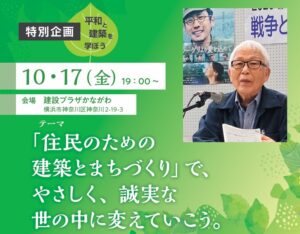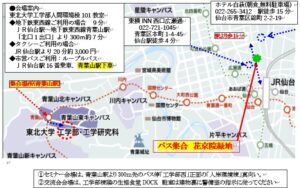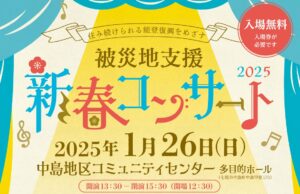日時:5月23日(金)19:00〜21:00
開催形式:Zoomによるオンライン開催
申し込み方法:メール madoguchi@nu-ae.com
お名前・所属・電話番号(メールが届かなかった場合のみ使用)をお書きの上、
メールでお申込みください。後日、ZoomのURLをお送りします。
今年の新建懇談会の第1回では、住宅研究者の中島明子さん(和洋女子大学名誉教授)をお招きし、住宅問題の現状についての話題提供をしていただきます。
中島さんは、「住まい」を単なる建築物ではなく、暮らしと社会の関係性から捉える視点で一貫した研究を続けてこられました。「東京民報」にて住宅問題に関する連載を執筆されており、その中で語られる内容は、私たちが直面する住宅の課題をより深く理解するための大きな手がかりとなるはずです。
5/23 中島明子さん話題提供 資料(PDF)
東京の住宅問題① 住まいは人権
「住まいは人権」という言葉を聞いた方はいるでしょう。「誰もが人間らしい住まいに住む権利がある」という意味のこの言葉は、第2次大戦後、国連「世界人権宣言」から引き継がれ、住まいを考える上で大事な理念となっています。
「誰もが」というのは、低所得者、高齢者、障害者、性的少数者、外国籍の人、災害被災者、そして家を失ったホームレス状態の人であっても、人である限りすべての人が、という意味です。それは「人間らしい住まい」というのは、単に屋根があればよいのではなく、そこで住む人や家族が安心して心地よく住めるものでなければなりません。近隣の人々との豊かな交流も大事です。
こうした住まいに住むためには住宅に関わる費用が必要です。家賃・維持管理費、住宅購入費やその住宅ローンの費用です。相続した家に住んでいても固定資産税や都市 計画税は払いますね。
ところが「東京の住まい」は、地価の高騰に連動して住居費が異常に高く、2024年には23区の新築分譲マンションの平均価格は1億1051万円と驚異的価格になり、民間賃貸住宅の平均家賃は8万8608円で、 全国平均6万1963円を大きく上回っています(2018年)。
また東京都の住宅の広さは都道府県で最低です。持家の平均床面積は93.3㎡(全国119.9㎡)、借家は40.8㎡(全国46.8㎡)となっています。借家が狭く、広い家に移ろうと思っても家賃や住宅価格が高く、もはや東京には住めない状況になってきました。
こうした状態を改善するのが「住宅政策」です。一定の質をもった低家賃の公共住宅の供給や家賃助成等の住宅費負担の軽減は、今日の非正規雇用等による低賃金や低年金・無年金の人々が増えている現状では、非常に重要なのです。しかし、東京都は2000年から都営住宅の新規建設は行なわず、家賃助成もやっておりません。
他方、東京都の特別区では8区で家賃助成が行われており、さらに杉並区が加わりました。 杉並区の岸本聡子区長は、「住まいは人権」に基づき、自治体でもできることがあるとして、住宅の公共性を念頭に、今年度から民間賃貸住宅における家賃補助制度を創設したのです。
「住まいは人権」は1990年代のバブル経済以降に広がりましたが、住宅政策への新自由主義の導入で後退しました。今それを打ち破る兆しが見え始めています。
次回から7回にわたり、「住まいは人権」の視点で東京の住宅問題を考えてゆきたいと思います。
東京の住宅問題② 高齢者はどこに住む
2025年は団塊世代が75歳となり、後期高齢者が前期高齢者を大きく上回るようになる年です。
24年の高齢化率は、東京都全体では23.5%で、全国の29.3%よりは低いのですが、地域によって異なり、奥多摩村では45%と高い一方、千代田区では19%です。いずれにしても10年後には約4人に1人が高齢者になると予想されています。
では東京の高齢者はどこに住んでいるのでしょう。
毎月の家賃が不要で、家賃の更新もない“持家”は、高齢期の生活の安定のセーフティネットの役割を担っています。
全国では82%が持家で、東京都は69%と少なくなりますが、やはり持家が一番です。但し、一人暮らしの高齢者世帯では、持家は52%と少なくなり、代わって民間借家が30%と多くなり、公営住宅・UR等と併せて借家暮らしが半数近くになっています。
では介護が必要になった時にどういう住宅を望んでいるでしょうか。2015年の国勢調査では「現在の住宅に住み続けたい」というのが半数近くです。認知症高齢者の約6割が居宅を希望し、介護保険サービスを使って何とか暮らしているのがわかります(2019年)。
最近は「サービス付き高齢者向け住宅」や「有料老人ホーム」(介護型、住宅型、健康型)も増えてきましたが、何と言っても既存住宅のバリアフリー対策や耐震改修、温熱環境を整え、住み慣れたところで安心して住み続けられるようにすることが重要です。
介護が必要になった時、前述の有料老人ホームの他、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム、ケアハウスなどの住まいがあります。
残念ながら現状では数が少なく金次第。低家賃であれば低質の事が多く、適切な家賃と質の高齢者住宅が必要です。
問題は、高齢になると民間賃貸住宅への入居が非常に難しくなることです。住宅仲介業者や家主さんは、高齢者の家賃滞納や孤独死をおそれるからです。特に女性の場合、低年金・無年金の場合や、夫と死別したために、家賃が払えなくなることもあるのです。
再開発等で立退きが増えていますが、高齢者は転居先の住宅確保が困難です。この場合は、自治体の居住支援協議会、東京借地借家人組合や弁護士に相談しましょう。
最後に、高齢期の住まいで大事なことは、人とのかかわり豊かな住まいで孤立しないことです。高齢期に入り一人暮らしの人も少なくありません。その住まいが、近隣とのつながりができる居住スタイルであれば、長生きにつながります。
東京の住宅問題③ 子育て世帯と住まい
日本の少子化が止まりません。一人の女性が生涯に産む見込みの子どもの数を「合計特殊出生率」といいますが、2023年には1.20で、日本は2011年以来、人口減少が続いています。政府は、日本の労働力不足や医療・介護の担い手不足等の危機感から、出生数回復に必死です。
そして、東京都の合計特殊出生率は全国最低で、近年には0.99になってしまいました。家賃・住宅費が高く、過密で自然が乏しい環境は、子育て世帯には住みにくいのです。子どものいる世帯では、子どもの発達に応じた住宅の広さや部屋数の確保と、安全な設備が必要です。また、近隣の遊び場や自然環境の確保も重要です。しかし、市場に依存した住宅政策の下では、低所得者が払える家賃では、狭小過密で低質な住宅にしか住めません。 そこで、先進諸国では、大都市でも適正な質の低家賃住宅に住めるよう、公的住宅や非営利住宅(社会住宅)の供給と、住居費軽減策として家賃補助や住宅ローン返済額の軽減を行っています。
しかし東京都では、社会住宅(都営住宅)は2000年以降、供給していませんし、家賃助成も現在はやっていません。
そうした中で2025年に登場したのが、子育て世帯などが都内で住宅を確保することを目的とした「アフォーダブル住宅」です。東京都と民間企業が100億円ずつ出資して総額200億円規模のファンドを設立し、空き家を活用するなどして、子育て世帯に手頃な値段、すなわち「アフォーダブル住宅」を供給しようとするものです。
欧米先進国の住宅政策においては、低・中所得者が支払える家賃の住宅を提供することを「アフォーダビリティの確保」として重視しています。低所得世帯も所得の3分の1以下の負担で適切な質の住宅に入居できることを目指し、その中心は社会住宅です。
では、東京都の「アフォーダブル住宅」は、子育て世帯にとって有効なのでしょうか?
確かに一部の中堅所得層にとっては良いかもしれませんが、低所得層にとっては家賃が高く、利用できません。困窮するひとり親世帯にとっても使えません。
なぜ都営住宅を拡充しないのでしょう。
東京都の子育て支援策としては、2023年から「東京こどもすくすく住宅認定制度」があります。この制度では安心して家事・育児をしやすい質をもった優れた住宅(共同住宅)を認定しようというものです。そうした子育てに配慮したデザインはどの住宅でも必要で、そうした質をもった住宅に、東京都23区内でも住めるように、家賃助成等の住宅費軽減への支援が必要です。
東京の住宅問題④ 自立できる若者の住まいを
東京は家賃が高く、若者にとって住みにくい都市です。大学に入学して下宿する学生は、高額な学費と合わせて家賃が重く、親に過大な経済的負担をかけるか、アルバイトで学ぶ時間を削るしかありません。東京の若者は、親の傘の下で住居費を節約するか、低質な賃貸住宅やシェアハウスに住むしか選択肢がないのです。
ところでシェアハウスというのは、本来、各自の専用の居室と、食事や交流ができる共同リビングがある居住スタイルです。共同生活により人間関係や民主主義を学ぶ、「自立」に向けての優れた準備空間なのです。
しかし供給されている物件は、専有部分が4畳半以下で、共同リビングもなく、共用トイレとシャワーだけで、半世紀前の木賃アパートの再生産ともいえるひどさです。
これは、「セーフティネット住宅」の基準を、東京都を含む大都市では、国の基準を緩和し、特にシェアハウスの場合は専用居室面積9㎡以上を、7㎡(4.2帖)以上に緩和したからです。
住宅セーフティネット制度は、民間借家の活用のよい機会でしたが、低質住宅にお墨付きを与えてしまい、そこに若者が住んでいるのです。
このような若者の住宅事情に対し、東京都は何をしているのでしょう。
都営住宅を活用した1年間の就労自立モデル事業や、大学との連携でコミュニティの活性化を図る事業等を展開しています。しかし、いずれも若者の安定した居住を行うものではありません。
大学との連携事業であるならば、学生向け共同住宅の供給をしたいものです。住宅セーフティネットの対象に困窮する学生を有資格者とし、空き家を改修し、大学が管理運営する方式です。
以前、新宿区では「学生及び勤労単身者向け家賃補助」制度が行われていました。バブル期で家賃の高騰に窮した大学院生等が陳情し採択されたものでした。「学生・若者は流動性が高いが、コミュニティの活性化の上で必要だ」等の理由で制定されたのです。
東京都の高家賃を考慮し、東京都として若者向け家賃助成を行う必要があります。
また、民間の例ですが、2023年に東京中小企業同友会台東支部が、区内の空き家を改修し、若手社員の「シェア社宅」として活用するプロジェクトを提案しました。「社宅」の枠を外し、中小企業が共同で若手社員の住宅を提供するのはよいアイデアです。東京都内で数少ない定住支援としては、奥多摩町の「町営若者住宅」があります。
若者が自立して暮らせるように、住宅政策に「若者の住まい」のカテゴリが必要です。
東京の住宅問題⑤ 震災対策と住まい
東京では、今後30年以内に70%の確率で、マグニチュード7程度の首都直下地震が発生すると予想されています。2022年の東京都防災会議では、揺れによる全壊家屋が約8万棟、建物倒壊による死者は約3200人と想定され、いかに被害を少なくするかが喫緊の課題です。
東京都は2023年に『耐震改修促進計画』を改定していますが、ここでは住まいについて考えてみましょう。
現在、新築住宅については、1981年の建築基準法の改正、さらに木造住宅に関して強化された2000年改正の基準によって建設されていますので、倒壊する危険は大分少なくなりました。
しかし、2023年改定の『東京都耐震改修促進計画』によると、住宅全体で耐震性を満たさない住宅が約756,000戸(約11%)あり、これらを改修・建て替えによってなくしていく必要があるのです。
したがって、都民の命を守る防災対策であり、住宅政策の基本として、既存住宅の耐震化が重要です。
地震があっても倒壊せず、火災の発生を減らし、軽微な修復で居住継続が可能となります。空地が少なく、仮設住宅を建設することが難しい東京では「仮設いらず」の対策は必須の課題です。
他方、低質な住宅を無くすことも重要です。低所得の人々にとっては低家賃の住宅でなければ住めず、それらは民間の「低質」で耐震性も低い住宅が大半です。いつまでも「貧困居住は自己責任だ」と放置しておけば、東京の住宅の耐震化率は上がらず、危険を温存することになるのです。
都内には木造住宅密集地域が19区54地区合計約3,000ヘクタールもあり、国、東京都と特別区で整備事業を行っています。そうした地域には高齢者が多く、地域が改善されるのはよいのですが、低所得の高齢者の転居には十分な配慮が必要です。
またこれら多くの地域では土地の所有関係が複雑だったり不明のため、改善は困難ですが、コミュニティの温もりがある地域もあります。若者が地域の活性化に貢献しているところもあります。災害時の助け合い等のソフトな活動が可能な地域に、新たな対策が生まれつつあります。
3月に出版された稲毛政信さんによる『耐震改修で地震を克服しよう』には、戦前にあった世界初の耐震基準等の良き耐震基準を、戦後の建築基準法制定時に切り下げてしまったことが、1981年の基準法改正まで耐震性不足の建物を生み出したとして、地震大国日本において「国の責任」であり、「耐震改修を受けることは、私たちの権利です」と述べています。
東京の住宅問題⑥ マンション ― 何が問題か
東京都の分譲マンション(以下「マンション」)の総戸数は、2020年には191万戸となり、全世帯の約4分の1を占めるようになりました。今や都民の主要な居住様式になっています。
しかし昨年の区部新築マンションの平均価格は1戸あたり1億円を超え、もはや庶民が購入できる価格ではなくなりました。要因は、都内各地で進む再開発によって超高層のタワーマンションが供給されて価格が吊り上げられ、それが周辺の地価やマンション価格の高騰につながっているからです。
タワーマンションは、投機的購入もあり、超高層での居住や周辺環境への影響、災害時の安全性等は明らかではなく、戸数規模も大きく、コミュニティの形成や維持管理のための合意形成も難しい形態です。
今日の東京のマンション問題の第一は、都民の生活空間が、資本によって歪められ奪われていることだといえるでしょう。
他方、着工から40年以上のマンションは、東京都によると2018年には24.6万戸でしたが、2043年には117.7万戸と予想され、世帯主の高齢化と併せ、「二つの老い」に直面しています。
ゼネコンや国・自治体は、高経年化したマンションの「建替え」を促進しようとしてきました。しかし立地や建物条件、区分所有者の事情や合意形成等の理由で非常に難しく、最近では長寿命化対策に向かうようになりました。 鉄筋コンクリート造の建物については、税法上の耐用年数は47年ですが、適正に施工されていれば40年程度で建替える必要はないのです。
建設後の維持管理と耐震改修によって、100年近く持つのです。さらに当初無かった防災・高機能化対策やコミュニティ関連の改修によって、若い世代を巻き込み、より価値の高いマンションにすることも可能です。
行政も管理組合も「中古マンション」とは言わず、「既存マンション」の価値を維持・発展させる方向で取り組みたいものです。
2019年に東京都は「マンション管理条例」を制定し、翌年から「管理状況届出制度」を開始し、適正管理の促進と、老朽マンション等の再生施策に取組んでいます。
最後に触れておきたいことは、マンションというのは、「共同居住の場」だということです。高齢化・少子化・単身化が進む東京で、人々がより心地よく暮らしていく上で、「共同居住」は不可欠の居住様式です。個々の住戸の確保と共に共同の場を住棟や地域に確保するようなマンションづくりにしたいものです。自ずと建物の高さは決まりますね。
東京の住宅問題⑦ 住まいに困った時に
「私は長生きしすぎたのかしら」と言って、区の居住支援相談窓口を去っていく80歳を超えた単身女性の姿が頭から離れません。高齢で単身で女性であれば、家主からは家賃の支払い能力や、孤独死等の不安によって避けられがちで、新しい住宅確保をすることが難しいのです。
高齢女性の場合、低年金の場合が多く、夫婦でいた時は家賃を払えても、配偶者が亡くなったとたん、家賃がはらえなくなるのです。老後も人間らしい住まいの家賃が払える年金が必要だと痛切に思います。
高齢者だけでなく、シングルマザーや非正規雇用の単身女性の貧困も、生きる上で必須の住まいの確保の困難につながっているのが現状です。最近では外国籍の人も含め、複合的困難を抱える女性も多くなりました。
特に住宅確保が難しいのは精神障害の方です。住宅に困窮した若者の中には精神障害者も少なくありません。適切なサポートがあれば自立した生活は可能です。また精神障害者が共同生活を行うグループホームがもっとあれば状況はずっと改善されるでしょう。
国は2006年に「住生活基本法」を制定しました。これは市場主義による住宅政策ですが、その第6条に「居住の安定の確保」を掲げ、低額所得者、被災者、高齢者等、住宅確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保を掲げています。翌年には通称「住宅セーフティネット法」が制定され、2024年の改正で今年の秋に施行されます。
そこでの柱の一つが「居住サポート住宅」です。居住支援法人等が要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつながりを行うもので、この住宅の供給促進を行います。既に2017年に「セーフティネット住宅」が導入され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない「登録住宅」と住宅確保要配慮者のみが入居できる10年期限の「専用住宅」があります。
東京都の住宅は「東京ささエール住宅」として閲覧できますが、空家は少なく、低家賃・底質住宅か高額家賃の住宅が掲載され、困窮する人々が入居するには量も質も不十分です。
そこに、単に箱だけを供給するには限界があるとして、新たに「居住サポート」が登場しました。穴だらけのセーフティネットに次々に絆創膏を貼っているようで、持続的施策しはいえません。
東京都は2022年度に5兆円を超える金融資産があると指摘されています。それを活用して「居住者支援を行う都営住宅」の供給と補完する民間借家への家賃助成を実現すべきです。
東京の住宅問題⑧ “住まいは人権” 広げよう
“住まいは人権”を掲げた学際的住宅研究組織「日本住宅会議」は、1982年に設立されました。
その趣意には「人間にふさわしい住居と環境を求めることは、すべての国民の基本的権利である」とうたわれ、以後40年以上にわたり活動を続けています。
1980年代はバブル経済によって東京の地価急騰に伴い、東京都23区は住宅価格も民間借家の家賃も急騰し、住み続けられない人々が増え、自治体存続の危機にもなりました。
都民の居住の危機に対し特別区では、それまで公営住宅や公団・公社住宅の供給程度だったところに、『住宅白書』を刊行し、住宅条例を制定し、住宅政策審議会等を設置して区民参加の道をつくり、新たに家賃助成や住宅付置義務等を導入しました。
それらは総合的な「住宅政策」というよりは、「定住促進」という側面が強かったのですが、基礎自治体である特別区において住宅政策を行うという点で画期的でした。
しかも、「新宿区の住宅及び住環境に関する基本条例」(1991年)と「世田谷区住宅条例」(1990年)に“住まいの権利”が掲げられたのです。大事なことは、これらが実現したのは、区民、若者、労働組合、住宅運動団体の強力な要求運動に呼応して自治体が実現したことです。
それから40年近く経ちました。住宅政策に新自由主義が導入され、東京都では、規制緩和による巨大再開発が推進され、バブル期を上回る程の住宅価格と家賃の狂騰が起こり、平均的都民でさえ住み続けられない事態になっています。
他方で、東京都には非正規雇用労働者の割合が約34%(2024年)になり、年収200万円以下の就業者は男性が約12%に対し、女性は約50%を占め、人間らしい住まいに住める家賃を捻出することが難しい人々、とりわけ住宅に困窮する単身女性が増えています。
杉並区の岸本聡子区長は「“住まいのことは権利だ”という視点に立つと、住宅政策は大きく変わってくる」と述べ、家賃補助を視野に入れて、基礎自治体でできる居住支援を実施し始めました。
今こそ、誰もが人間の尊厳をもって暮らせる“住まいの権利”を基盤にした住宅政策を実現したい。何よりも安全・安心で、家族や人々と自然とのかかわり豊かな空間で、支払える家賃・住宅費の住まいです。
それは待っていても実現しない。若者・高齢者・女性・ひとり親・障害者・LGBTQの人々・外国籍のある人、そして子ども、といった都民による「住まいをよくする活動」にかかっているのです。