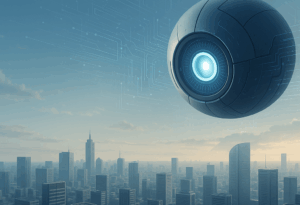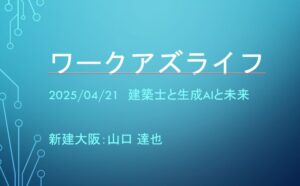建設五会による2025年5月の提言の中で「一級建築士資格制度」に対して、住民のための住まい・まちづくりの視点が欠落しているのではないかという問題意識をもとに、書いてみました。
提言本文
JIAのHPに全文が掲載されています。

一級建築士制度の将来像に抱く違和感
2025年5月、建設五会が発表した「国際的で魅力ある次世代の建築職能人材の育成に向けた提言」。一級建築士制度の国際的な信頼性や教育の整合性、そして試験制度の見直しに至るまで、非常に丁寧に議論が重ねられています。しかし、この提言を読み進めるにつれ、ある“違和感”が拭えなくなってきました。それは、「住民の生活」や「地域のまちづくり」という視点がほとんど見当たらないという点です。
どれほど制度を整えても、それが誰のためにあるのかという問いに答えなければ、どんなに素晴らしい建築教育も、単なる“資格ビジネス”になってしまいます。読みながら、「この提言は誰のためのものなのだろう?」という疑問が頭をよぎりました。
グローバル化と資格制度は、どこへ向かうのか
提言のなかでは、「一級建築士資格の国際的信用性」が繰り返し語られています。確かに、国際化が進む現代において、日本の建築士資格が世界で通用するようになることは重要です。しかし、資格制度を“国際比較の道具”としてばかり考えることで、見落としてしまうものもあるのではないでしょうか。
例えば、ある地方の被災地で、地域住民とともに仮設住宅の集会所を設計していた建築士は、国際的評価とは関係なく、地域に根ざした実践的な知恵を持っていました。今回の提言の流れを見ていると、こうした建築士の価値が制度の中で見過ごされてしまうのではないかという不安を感じます。
住民の生活は、提言のどこにあるのか
提言には「建築界・専門職能の魅力を向上させる」といった言葉が並んでいます。しかし、「建築士として住民と直接向き合う姿勢」——たとえば、まちづくりへの参画や地域防災への貢献、子どもの遊び場をどのようにつくるかといった視点——は、ほとんど見当たりません。
これは例えるなら、レストランの厨房だけをピカピカにしておいて、「食事はまあ適当でいいでしょう」と言っているようなものです。どれだけ厨房が立派でも、食べる人の顔を思い浮かべない料理に価値があるとは思えません。
「建築士=受験テクニシャン」
大学卒業後、すぐに受験できるようになった試験制度の変更は、変更前から大学が資格予備校化する懸念がありましたが、大学院修士課程1年という最も研究に没頭できる時期に建築士試験勉強に時間を費やしているという実態も明らかになっています。
現在の試験制度は、「何年かかっても合格しないといけない超難関ゲーム」と化しており、しかもその試験内容が実務とはずれているとの指摘も多くあります。その結果、建築士を目指す人が“受験テクニシャン”になってしまっているのではないでしょうか。
提言では、「試験が実務と乖離している」「学業が空洞化している」といった現場からの懸念も紹介されていますが、それは予測できていたことです。
さらにこれらの提言は、あくまで「効率的な人材育成」の視点にとどまっており、「住民の信頼を得る建築士を育てる」といった視点は感じられません。
資格制度の再設計に求められる住民視点
そろそろ私たちは問うべき時期に来ています。「一級建築士とは、何をする人なのか?」という根本的な問いをです。本来、地域の課題を読み取り、住民と共にまちをつくる存在が建築士であるはずです。であれば、その資格制度も「共に暮らす視点」を持つべきではないでしょうか。
例えば、二次試験の製図試験の代わりに「地域住民との対話を模擬するグループワーク」や「空き家再生プランを住民に説明し、理解を得るプレゼンシナリオ」をつくる。そんな現場感のある評価方法があっても良いと思います。
「人と人との関係性をつなぐ技術」へ
建築士資格は、単なる「制度」ではなく、「人と人との関係性をつなぐ技術」を育む場であってほしいと思います。国際競争力を高めることも大切ですが、それと同じくらい、「暮らしに根ざした知恵」こそが、これからの建築士に求められる力なのではないでしょうか。AIが導入されていく中で、建築士に求められる職能は大きく変化しています。
一級建築士は、建物を設計できるだけではなく、「人の声を聴ける人」であってほしい。
なぜなら、私たちは建築の中で生きているのですから。
このような視点から、資格制度と職能の本質を問い直すことが、これからの制度設計には欠かせないと感じています。
<文責:大阪支部 山口 達也>