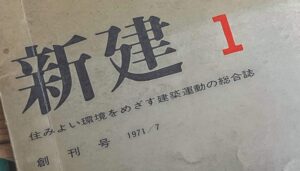3月号の特集は「次世代に遺す①建築保存」です。本年は様々な意味での節目に当たり、豊かさの再構築という視点からも、取り上げたいテーマです。
index<特集> 次世代に遺す① 建築保存
今年は戦後80年ということで「次世代に遺す」をキーワードに年間企画を考えました。第一弾として「建築保存」を取り上げます。
文化財保護法は1950年に施行され、今年で75年になります。それまでの国宝保存法、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律、史蹟名勝天然記念物保存法の三法が統合されたもので、「文化財」の概念が定義された画期的な法律だったといいます。国が厳選した文化財を手厚く保護していく国宝や重要文化財の制度は、凍結保存とも揶揄されますが、法隆寺金堂壁画が焼失したのをきっかけに法律が制定されたことを考えれば、当然のことかも知れません。1975年の改正により発足した伝統的建造物群保存地区の制度は、単体だけでなく線や面としての保存が進められ、その地域らしさ、町並み保存の大きな力になりました。1996年の改正では、登録有形文化財の制度がつくられ、緩やかな規制のもとに、多くの身近な無名の建物の歴史的・文化的価値を再発見するきっかけともなりました。その他の法律改正や制度の拡充を受けて、文化財保護、建築保存の意味も範囲も大きくなってきています。
2019年に改正された内容については、やや注意が必要です。保存よりも活用が前面に表現され、活用ありきで保存・保全をないがしろにしかねず、活用できないもの・お金を生み出さないものは文化財ではないとまで言い切る人もいるためです。もちろん文化財保護法第1条において、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」が目的として掲げられているので、文化財を活用することは望ましい面もあります。文化財としての価値を後世に向けて確実に維持する「保存」と、文化財としての価値を踏まえ適切に現代社会に生かす「活用」の両立を目指すこと、そのバランスを間違ってはいけないのだと思います。
いずれにせよ、文化財の範囲が多岐にわたり、文化財と名前をつけずとも地域にとって大事な建築やその集合体としての景観、風景が多くの人に認識されるようになってきました。それぞれの地域で守られてきたもの、守りたいもの、遺していきたいものを報告します。
担当編集委員/桜井郁子、古川学建まち2025年3月号から引用
あらためて問いたい次世代に遺す指標としての建築保存とは
今、私たちが歴史的な建物や街並みを守る意味は、単なる「昔のものを残す」ことだけではありません。私たちが住んでいる地域や、これから子どもたちが大人になったときに暮らす場所が「どのような価値観や生活スタイルを持った社会であってほしいか」を考えることにつながっています。
例えば、空き家になった古い建物をカフェやゲストハウスとして生まれ変わらせることで、新たなコミュニティが生まれ、地域の活性化につながります。昔から続く祭りや伝統行事の場として街並みを生かし続けることで、次の世代に文化や暮らしの知恵を伝えることができます。
私たちが今大切にしなければならないのは、「残すこと」と「暮らし続けること」のバランスではないでしょうか。建築を保存することは、ただの古いものの保護ではなく、次世代へのメッセージです。「私たちはどのような未来を望んでいるのか」、建築保存を通して、もう一度考えてみる必要があります。
<文責:大阪支部:山口達也>